「うちの子、もっと自分で考えて行動してほしい」
「親がいちいち言わなくても、自分でやる気を出してくれたら…」
今回は、そんなサッカーママ・パパたちにぜひ手に取っていただきたい一冊
『7つの習慣』(スティーブン・R・コヴィー著)をご紹介します。
ビジネス書の名著として広く知られている本書ですが、実は「子育て」の文脈でも非常に多くの示唆を与えてくれる内容なのです。
この記事では、『7つの習慣』の要点を整理しながら、サッカーに打ち込む子どもたちの成長を支える親の在り方について、実践的なヒントをお届けします。
『7つの習慣』とは?
スティーブン・R・コヴィー氏による『7つの習慣』は、全世界で3000万部以上を売り上げた、自己啓発書の金字塔ともいえる一冊です。本書が伝えるのは「人格主義」に基づいた人生哲学。目先の成功ではなく、「他者からの信頼」や「責任感」、「誠実さ」といった“内面の土台”を築くことの重要性を説いています。
この「人格を育む」という視点は、まさに子どもの成長に不可欠な要素。だからこそ、サッカーママ・パパにとっても学ぶ価値があるのです。
子育てに活かす『7つの習慣』
以下では、『7つの習慣』を1つずつ紹介しながら、サッカーママとしてどのように子どもとの関わりに活かせるかを解説していきます。
第1の習慣:主体的である
「自分の人生に責任を持つ」
「環境や他人のせいにしない」
これは、サッカーをプレーする時にも通じるマインドです。たとえば、試合で負けたとき、「味方のせい」「監督が悪い」と言うのではなく、「自分にできたことは何か」を考えられる子どもに育てたいものです。
ママとしては、「何でちゃんとやらないの?」と責めるのではなく、「自分でどうしたいと思った?」と問いかけることで、子どもの主体性を引き出すサポートができます。
第2の習慣:終わりを思い描くことから始める
これは「目的を持って行動する」という習慣です。
サッカーに夢中な子どもに対して
「将来どうなりたいの?」
「今、どんなプレーヤーを目指してる?」
などと問いかけることで、ただ漫然とボールを追うのではなく、自分なりのゴールを見据えて努力する姿勢を育むことができます。
親としても、目先の勝ち負けに一喜一憂するのではなく、「サッカーを通じてどんな人間に育ってほしいか」という視点を持つことで、子どもとの関わり方が変わります。
第3の習慣:最優先事項を優先する
現代の子どもたちは、サッカーの練習に加えて、学校、塾、友達付き合い…と忙しい日々を送っています。
この習慣は、「本当に大事なことを見極めて、時間とエネルギーをそこに注ぐ」という考え方。
親として、「勉強しなさい!」「早く寝なさい!」と口うるさく言うのではなく、「いま一番大事なことは何だろう?」と一緒に考えることで、だんだんと時間管理能力や優先順位のつけ方を身につけていけるはずです。
第4の習慣:Win-Winを考える
チームスポーツであるサッカーにおいて「自分が良ければそれでいい」という考えは通用しません。仲間との関係を大切にし、全体の成果を考える視点が求められます。
Win-Winとは、「自分も相手も互いに満足する道を探る姿勢」、その関係性の中に必要不可欠なものが「豊かさマインド」です。
自分の強み・味方選手の武器はなにか?
その武器を活かすために、自分にはどんなプレーができるか?
自分の強みを発揮するために、味方にどんなプレーをしてほしいか?
豊かさマインドを持つことで、自分も味方も持てる力の最大限を発揮し、高いレベルのWin-Win関係を築いていけるのです。
第5の習慣:まず理解に徹し、そして理解される
親として、つい「ちゃんと聞きなさい!」「ママ(パパ)の言うことを分かって!」と、言いたくなってしまいます。でも、この習慣はまず“子どもを理解すること”を優先します。
サッカーの試合後、子どもがふてくされた様子で帰ってきたとき
「何やってるのよ、もっと走らなきゃダメじゃない!」
ではなく
「悔しかったんだね」
「どんな気持ちだった?」
と耳を傾けること。
その上で、「ママ(パパ)はこう思ったよ」と自分の考えを伝えることで、親子の信頼関係は格段に深まります。
第6の習慣:シナジーを創り出す
「1+1が2ではなく、3にも4にもなる」――それがシナジーです。
たとえば、サッカーの中でも、個々の選手の技術が融合してチームとして最高のパフォーマンスを発揮する場面があります。これはシナジーの力。
家庭の中でも、きょうだい・家族で協力して目標を達成する経験を通じて、子どもは“共創”の力を学びます。
親がすべてのことを決めるのではなく、「どうしたら家族・チームのみんながハッピーになれるか」を一緒に考えることが、子どもの社会性や協働力を高めます。
第7の習慣:刃を研ぐ
これは、「自分自身のメンテナンスを怠らず、リフレッシュして成長を続けよう」というメッセージです。
子どもにとっても、毎日サッカー漬けでは心も体も疲弊してしまいます。あえて「遊ぶ時間」「休む時間」「読書の時間」などを取ることも大切です。
親自身も同様。子ども中心の生活の中で、自分の時間を確保し、自分を満たすことは、より良い子育てにもつながります。
これは、自分を形づくる4側面(肉体、精神、知性、社会・情緒)について、常日頃から管理し、さらに自己投資をしていくことで”再新再生”を図ります。
肉体:
栄養バランスの取れた食事とり、運動だけでなくリラックスのための休養を取ることが、自分の身体をメンテナンスするうえで必要になります。親子で一緒に取り組むストレッチや、リラックスできる入浴時間、十分な睡眠時間の確保も大事ですよね!
精神:
心に栄養を与えることで、リフレッシュ効果が期待できます。例えば、読書をしたり、リラックスできる空間、気のおけない友だちや家族との時間を過ごすことも、親子の心にとって重要です。
知的:
サッカー選手において、実際に自分がプレーするだけでなく、プロの試合を観て学び、豊かなプレーイメージを蓄えることも重要です。また、サッカーノートを継続して書くことで、自分の感情や目標に至る過程を整理してみましょう。
社会・情緒:
正しい原則に基づいた価値観を持つことや、自分の得意な分野で人の役に立つことが、自身を再新再生していくことに繋がります。例えば、チームで下級生になにかを教える経験や、困っているチームメイト・保護者を助けるなど、誰かのために自身で選んだ行動が、子どもを飛躍的に成長させるのです。
まとめ:子どもの“主体性”を育てるために
『7つの習慣』は、目に見える成果だけを追うのではなく、「人としてどうあるか」という“土台”を育てるためのヒントが満載です。
サッカーを通じて学べることは、勝つことや技術の向上だけではありません。困難に立ち向かう力、仲間と協力する力、自分の頭で考えて行動する力——これらを育てるために、ママとしてどんな関わりができるか。
その答えのヒントが、この一冊には詰まっています。
日々の送迎や応援に加え、精神的なサポートまで担うサッカーママ・パパだからこそ、『7つの習慣』を読む価値があります。子どもの未来を信じ、主体性ある成長を後押ししたいすべてのママ・パパへ、心からおすすめしたい一冊です。
サッカーママ・パパ、今日もお疲れ様です!

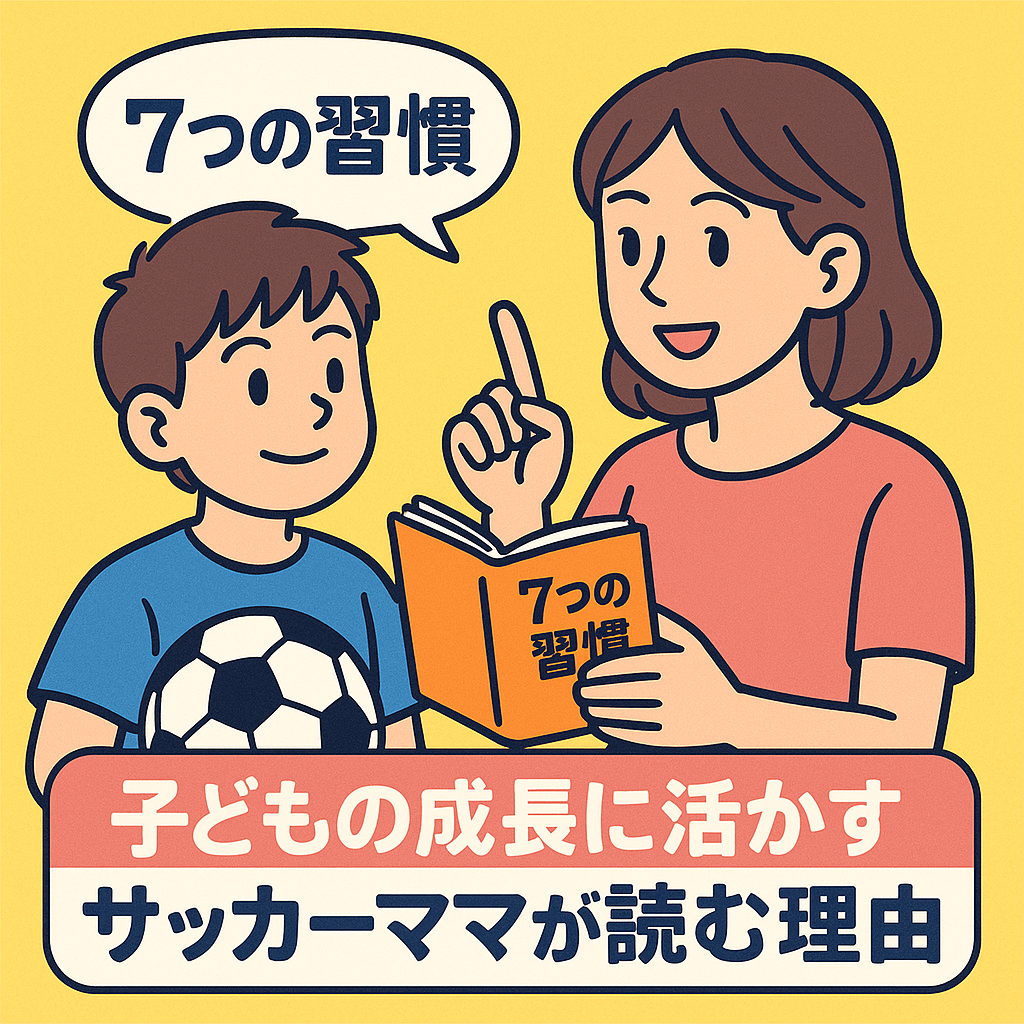


コメント